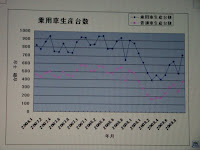今、やっている正倉院展に11月7日に行ってきた。年に一回の宝物の曝涼・日干しを利用しての展示で、奈良では風物詩になっているらしい。
正倉院と言えば、美術や歴史でアジア、ヨーロッパを結んだ古代の交易路(シルクロード)の執着点で、西方の影響を受けた工芸品が多く保管されていると聞いていた。一度は見なければと思っていたが、今まで機会がなかった。
ところが、正倉院の宝物に、752年の東大寺大仏の開眼供養で使用された調度類や聖武天皇の49日忌に光明皇后が献納した品物も納められ、今回は天皇即位20年を記念して、その中で66点が出展されているという。
市内は込んでいる。早めに駐車場に車を止めて奈良国立博物館に向かうが、人の波はみなそっちに向かっている。案の定、入場者の列が長い。案内人が白いボックスで入場券を買って列に並べという。「最後尾はここ」のプラッカードが出ている。看板には「60分待ち」の表示だ。
博物館の軒下部分では、3重に列が折れて入場口までノロノロ進むことになった。やっと入場でき2階の展示場に向かうと、女性の案内人が「立ち止まらず見てください。展示品を順番に関係なく見てください」という。
かなり前、学生時代に「ミロのヴィーナス」が日本に来て、京都での公開に行ったが、この時も警備員が「立ち止まらないでください。ドンドン進んでください」と声を張り上げていたのを思い出す。
じっくり落ち着いて鑑賞する習慣にかけている。案内人はドンドン見学者を捌いた方が良いのだろうが、見学者にとっては折角来たのだからじっくり見たいと思うだろう。
まず展示されている花氈(かせん)が目にとまった。山羊の毛を圧縮したフェルトの敷物だ。今で言う絨毯か。材質を活かし豪華に染め上げている。
紫檀木画槽琵琶(したんもくがそうのびわ)は唐代の琵琶で、背面に花、鳥を画き、ツゲや象牙、シカ角などの素材をはめ込んだ木画技法を採用に豪華な仕上げになっている。国際色豊かな琵琶で、見学者が釘付けになっている。五面現存する四弦琵琶の一つだという。この琵琶で奏でた曲が流れていた。素人目からすると、いろんな素材をはめ込まない方が良いのではないかと思うのだが。
これらの琵琶を包んだ袋の残骸?(琵琶袋残欠)も展示されている。ここまで来たら普通はポイするだろうが、よく保存されているモノだと感心する。
当時貴族で盛んに行なわれていた碁盤、桑木木画棊局(くわのきもくがのききょく)はヒノキの板に木目のある桑の薄皮を張り合わせたモノで、これも木画技法を駆使している。
貴族の使うモノは、遊び道具とは言え手が込んでいる。
光明皇后が、書の名人・王義之が書写した手本をもとに、44歳の時に書いた楽毅論(がっきろん)は、その力強い筆運びは評価が高い。王義之と言えば、高校の時の書道でその作品の一部を手本にしたことがある。意味を先生が説明してくれたので、何のことかは分かったが、この展示ではどんな内容の書かは分からない。意外にこんなモノはその内容は難しくないモノだ。
伎楽面(ぎがくめん)呉女(ごじょ)は光明皇后の顔を思わせるという。小さな顔だったが、優しさを持っていたように感じた。
図書、調度品、皿、楽器、遊戯具、佛具など、どの出展物も豪華で、木画技法を駆使した貴重はモノばかりだ。
しかし、庶民の生活とはかけ離れた文化であり、「すごかったはネ」以外の感想が出てこない。後はグッヅ売り場で、みやげモノ買いだ。ここでも「レジの最後尾はこちら」との表示が出ている。
ここで、大森貝塚を発掘調査したモースさんの言葉を思い出す。「日本人って、豪族などの遺品は大事に保存するが、庶民の使っていたモノは大事にしない。これでは庶民の生活など理解できない」という。人類学者らしい考えだ。モースさんは、当時の庶民の生活様式をスケッチしたり、庶民が使ったと思われる出土品を沢山集めて、アメリカへ持ち帰ったらしい。
地方を旅行したときに、博物館、美術館に行くとその地方の豪族や藩主が金に糸目を付けず、かき集めた美術品が多数展示されている。一方で民族館に行くと庶民の生活必需品が展示され、当時の生活が偲ばれる。子供の時、これに似たものがあったことを思いだす。
自分の身分とはかけ離れた別世界の文化には、国民の共有のモノと言うがスンナリとは入っていけない。専門家や研究者の間での共有物でしかないのか。
帰りに興福寺の阿修羅展に行ってみたが、2~2.5時間待ちで残念ながら止めた。
正倉院と言えば、美術や歴史でアジア、ヨーロッパを結んだ古代の交易路(シルクロード)の執着点で、西方の影響を受けた工芸品が多く保管されていると聞いていた。一度は見なければと思っていたが、今まで機会がなかった。
ところが、正倉院の宝物に、752年の東大寺大仏の開眼供養で使用された調度類や聖武天皇の49日忌に光明皇后が献納した品物も納められ、今回は天皇即位20年を記念して、その中で66点が出展されているという。
市内は込んでいる。早めに駐車場に車を止めて奈良国立博物館に向かうが、人の波はみなそっちに向かっている。案の定、入場者の列が長い。案内人が白いボックスで入場券を買って列に並べという。「最後尾はここ」のプラッカードが出ている。看板には「60分待ち」の表示だ。
博物館の軒下部分では、3重に列が折れて入場口までノロノロ進むことになった。やっと入場でき2階の展示場に向かうと、女性の案内人が「立ち止まらず見てください。展示品を順番に関係なく見てください」という。
かなり前、学生時代に「ミロのヴィーナス」が日本に来て、京都での公開に行ったが、この時も警備員が「立ち止まらないでください。ドンドン進んでください」と声を張り上げていたのを思い出す。
じっくり落ち着いて鑑賞する習慣にかけている。案内人はドンドン見学者を捌いた方が良いのだろうが、見学者にとっては折角来たのだからじっくり見たいと思うだろう。
まず展示されている花氈(かせん)が目にとまった。山羊の毛を圧縮したフェルトの敷物だ。今で言う絨毯か。材質を活かし豪華に染め上げている。
紫檀木画槽琵琶(したんもくがそうのびわ)は唐代の琵琶で、背面に花、鳥を画き、ツゲや象牙、シカ角などの素材をはめ込んだ木画技法を採用に豪華な仕上げになっている。国際色豊かな琵琶で、見学者が釘付けになっている。五面現存する四弦琵琶の一つだという。この琵琶で奏でた曲が流れていた。素人目からすると、いろんな素材をはめ込まない方が良いのではないかと思うのだが。
これらの琵琶を包んだ袋の残骸?(琵琶袋残欠)も展示されている。ここまで来たら普通はポイするだろうが、よく保存されているモノだと感心する。
当時貴族で盛んに行なわれていた碁盤、桑木木画棊局(くわのきもくがのききょく)はヒノキの板に木目のある桑の薄皮を張り合わせたモノで、これも木画技法を駆使している。
貴族の使うモノは、遊び道具とは言え手が込んでいる。
光明皇后が、書の名人・王義之が書写した手本をもとに、44歳の時に書いた楽毅論(がっきろん)は、その力強い筆運びは評価が高い。王義之と言えば、高校の時の書道でその作品の一部を手本にしたことがある。意味を先生が説明してくれたので、何のことかは分かったが、この展示ではどんな内容の書かは分からない。意外にこんなモノはその内容は難しくないモノだ。
伎楽面(ぎがくめん)呉女(ごじょ)は光明皇后の顔を思わせるという。小さな顔だったが、優しさを持っていたように感じた。
図書、調度品、皿、楽器、遊戯具、佛具など、どの出展物も豪華で、木画技法を駆使した貴重はモノばかりだ。
しかし、庶民の生活とはかけ離れた文化であり、「すごかったはネ」以外の感想が出てこない。後はグッヅ売り場で、みやげモノ買いだ。ここでも「レジの最後尾はこちら」との表示が出ている。
ここで、大森貝塚を発掘調査したモースさんの言葉を思い出す。「日本人って、豪族などの遺品は大事に保存するが、庶民の使っていたモノは大事にしない。これでは庶民の生活など理解できない」という。人類学者らしい考えだ。モースさんは、当時の庶民の生活様式をスケッチしたり、庶民が使ったと思われる出土品を沢山集めて、アメリカへ持ち帰ったらしい。
地方を旅行したときに、博物館、美術館に行くとその地方の豪族や藩主が金に糸目を付けず、かき集めた美術品が多数展示されている。一方で民族館に行くと庶民の生活必需品が展示され、当時の生活が偲ばれる。子供の時、これに似たものがあったことを思いだす。
自分の身分とはかけ離れた別世界の文化には、国民の共有のモノと言うがスンナリとは入っていけない。専門家や研究者の間での共有物でしかないのか。
帰りに興福寺の阿修羅展に行ってみたが、2~2.5時間待ちで残念ながら止めた。