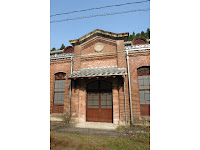今回の鳩山首相の所信表明は、今までの格式や専門用語を駆使した官僚から提出された施策を並べ替えたモノではなく、鳩山さんの体験から言いたいことを述べたところに、理念だけと批判されているが、何か心地よい響きを保っている内容だった。
住民が主役の地域、国造り、暮らしの豊かさに力点をおいた経済、人と人が支え合う役に立ち合う、一人一人が参加する「新しい公共」、「役に立つ」「必要とされる人間」として社会の中で自らの「居場所と出番」を見つけ事の出来る社会を構築する理念は、今まで忘れがちだった理念を再確認してくれるモノだった。
今までの自民党政権での経済成長路線、効率化優先の市場主義経済の追求から顕在化してきた格差社会の反省から、人間重視の経済への転換は当然のことである。
鳩山首相は、今回の選挙の勝利者は国民一人一人だという。しかし、国民は民主党を選択出来たことで勝利したわけではない。愛想を尽かせた自民党政権を今回だけは避けたのだ。戦後の行政のムダ、悪因習を蔓延らせたのには、野党だった民主党にも責任があるのは確かだ。穿った見方をすれば、勝利者と思っているのは、小沢さん一人ではないのか。
これからやろうとしている「戦後行政の大掃除」は自民党政治を180度転換する大きな挑戦であり、鳩山さんは「躓くこともあるだろう」「頭を打つこともあるだろう」と言及している。
ところが、既にその兆候は見えている。所謂小沢さんとの「二重権力構造」だ。これは総選挙前から見識者は心配していたことであるが、民主党の組織作りの段階で顕在化してきた。「それ見たことか」と思っている人は多いはずだ。
改革の方向、政治を根本から見直す長期戦略のための国家戦略室の構想がよく分からない。「行政の大掃除」をするのであれば、一番活躍しなければならない菅さんの存在が薄いことに気が付いていたが、「菅外し」を覆すために特別に菅副総理に言及しなければならなかった事情も政権党内の実情を伺わせる。
更に異例のことは、自らの政治資金規正疑惑にも言及しなければならなかったことだ。国民の政治不信を払拭するためには、政治家一人一人が襟を正さなければならないが、鳩山さん本人がその疑惑のど真ん中にいる。他人の疑惑の時は、「説明責任を」とコメントしていたが、自分の事になると歯切れが悪くなる。
小沢さんも公設秘書が起訴された。臨時国会では、民主党は代表、幹事長2人が、政治資金規正法で自民党からの攻撃の対象になる。
常識で考えれば、2人共に首相や与党幹事長の職に就くべきではないと思うが、大きな政局になる可能性は十分に考えられるが、そんなことに時間を費やす余裕など今の国政にはない。
何よりも重要で最優先課題は、雇用対策だ。緊急雇用対策本部を立ち上げて、失業者支援、雇用創出に取り組むという。しかしこれは並大抵のことではない。雇用を創出しようと思えば、企業の業績回復が必要であるが、それには消費の拡大が前提になる。
家計収入の増加、将来の不安の解消などいろんな政策が絡んでくる。今政策に上がっている子供手当、暫定税率の廃止、高速道の無料化などは家計の可処分所得を増大させるが、一方で価格競争は企業収益を減少させ、給料の減額、人件費の削減のためのリストラなど悪循環が続いている。
雇用対策で失敗すれば、国民の信を失い、政権の座から転がり落ちる。今、民主党政権は自民党政権の政策の180度転換を目指しているように見えるが、「何だ、自民党政権の方がまだマシだったのではないか」と考えるようになる可能性も大きい。
理念を実現する政策に緊張感を保って当たらなければ、国民に飽きられる日は直ぐそこに来ている。党内の権力闘争など御法度だ。
住民が主役の地域、国造り、暮らしの豊かさに力点をおいた経済、人と人が支え合う役に立ち合う、一人一人が参加する「新しい公共」、「役に立つ」「必要とされる人間」として社会の中で自らの「居場所と出番」を見つけ事の出来る社会を構築する理念は、今まで忘れがちだった理念を再確認してくれるモノだった。
今までの自民党政権での経済成長路線、効率化優先の市場主義経済の追求から顕在化してきた格差社会の反省から、人間重視の経済への転換は当然のことである。
鳩山首相は、今回の選挙の勝利者は国民一人一人だという。しかし、国民は民主党を選択出来たことで勝利したわけではない。愛想を尽かせた自民党政権を今回だけは避けたのだ。戦後の行政のムダ、悪因習を蔓延らせたのには、野党だった民主党にも責任があるのは確かだ。穿った見方をすれば、勝利者と思っているのは、小沢さん一人ではないのか。
これからやろうとしている「戦後行政の大掃除」は自民党政治を180度転換する大きな挑戦であり、鳩山さんは「躓くこともあるだろう」「頭を打つこともあるだろう」と言及している。
ところが、既にその兆候は見えている。所謂小沢さんとの「二重権力構造」だ。これは総選挙前から見識者は心配していたことであるが、民主党の組織作りの段階で顕在化してきた。「それ見たことか」と思っている人は多いはずだ。
改革の方向、政治を根本から見直す長期戦略のための国家戦略室の構想がよく分からない。「行政の大掃除」をするのであれば、一番活躍しなければならない菅さんの存在が薄いことに気が付いていたが、「菅外し」を覆すために特別に菅副総理に言及しなければならなかった事情も政権党内の実情を伺わせる。
更に異例のことは、自らの政治資金規正疑惑にも言及しなければならなかったことだ。国民の政治不信を払拭するためには、政治家一人一人が襟を正さなければならないが、鳩山さん本人がその疑惑のど真ん中にいる。他人の疑惑の時は、「説明責任を」とコメントしていたが、自分の事になると歯切れが悪くなる。
小沢さんも公設秘書が起訴された。臨時国会では、民主党は代表、幹事長2人が、政治資金規正法で自民党からの攻撃の対象になる。
常識で考えれば、2人共に首相や与党幹事長の職に就くべきではないと思うが、大きな政局になる可能性は十分に考えられるが、そんなことに時間を費やす余裕など今の国政にはない。
何よりも重要で最優先課題は、雇用対策だ。緊急雇用対策本部を立ち上げて、失業者支援、雇用創出に取り組むという。しかしこれは並大抵のことではない。雇用を創出しようと思えば、企業の業績回復が必要であるが、それには消費の拡大が前提になる。
家計収入の増加、将来の不安の解消などいろんな政策が絡んでくる。今政策に上がっている子供手当、暫定税率の廃止、高速道の無料化などは家計の可処分所得を増大させるが、一方で価格競争は企業収益を減少させ、給料の減額、人件費の削減のためのリストラなど悪循環が続いている。
雇用対策で失敗すれば、国民の信を失い、政権の座から転がり落ちる。今、民主党政権は自民党政権の政策の180度転換を目指しているように見えるが、「何だ、自民党政権の方がまだマシだったのではないか」と考えるようになる可能性も大きい。
理念を実現する政策に緊張感を保って当たらなければ、国民に飽きられる日は直ぐそこに来ている。党内の権力闘争など御法度だ。